荒川豊藏 / あらかわとよぞう
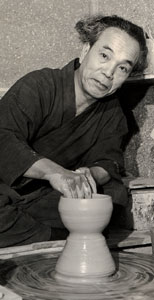
陶歴
- 1894年
- 3月17日、岐阜県土岐郡多治見町(現・多治見市)に生まれる。
- 1906年
- 多治見尋常高等小学校高等科2年修業。
神戸の貿易商・能勢商店に就職。
- 1911年
- 妻志づと結婚。
- 1919年
- 京都・宮永東山を知る。
- 1922年
- 京都・東山窯の工場長になる。
- 1927年
- 北大路魯山人の北鎌倉の星岡窯の窯場主任となる。
- 1930年
- 大萱の牟田洞古窯跡で志野茶碗銘玉川と同じ志野筍絵陶片を発見。
- 1933年
- 郷里に戻り、独立。
陶片を発見した大萱に穴窯を築いて初窯を焚くが失敗。
- 1940年
- 大阪阪急百貨店で初の個展「荒川豊蔵作陶並絵画展覧会」
- 1942年
- 桃山ルネッサンスと陶芸の近代化を目指し、川喜田半泥子、金重陶陽、三輪休和等と「からひね会」を結成する。
- 1946年
- 多治見・虎渓山永保寺所有の山を借り、水月窯を築く。
- 1955年
- 重要無形文化財技術保持者(志野・瀬戸黒)認定。
日本橋三越にて「荒川豊藏作陶展」開催。
- 1971年
- 文化勲章受賞(同日に文化功労者として顕彰)。
- 1977年
- 大阪高島屋にて「五窯歴遊・荒川豊藏展」開催。
- 1984年
- 財団法人 豊蔵資料館開館。
- 1985年
- 8月11日死去(享年91歳)

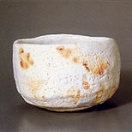
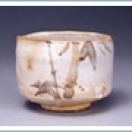

「志野」発見から3年後、39歳のとき、魯山人のもとを離れ、「志野」発見の地である大萱に、桃山時代と同じ単室窖窯を築いて作陶活動を始め、茶陶を主として桃山の志野、瀬戸黒、黄瀬戸などの研究を重ね、その復興に全力を注いだ。
当初は、桃山写しの作を創作していたが、徐々に独自の芸術性豊かな作風を展開した。